2025年は、日本の介護保険制度にとって大きな転換点となります。
高齢者人口の急増と財源の逼迫を背景に、制度の見直しが進められており、利用者やその家族にとっても少なからぬ影響が予想されます。
特に75歳以上の方や、今後介護サービスの利用を検討している方にとっては、今のうちに準備しておくことが、安心した老後の暮らしにつながります。
■ 介護保険制度の「2025年問題」とは
そもそも「2025年問題」とは、団塊の世代(1947~49年生まれ)がすべて75歳以上になる年を指します。
この年を境に、後期高齢者の人口が急増し、医療や介護の需要が爆発的に増えると見込まれています。
その結果、現行の介護保険制度では財政が維持できず、見直しを迫られているのです。
■ どんな改正が予定されているのか?
現時点(2025年7月)で検討されている主な改正点は以下の通りです。
◇ 利用者の自己負担割合の見直し
現行では、原則1割負担で利用できる介護サービスですが、一定以上の所得がある方は2割・3割と増えます。
2025年以降、この「一定以上の所得」の基準が引き下げられ、中所得者層にも2割負担が広がる可能性があります。
これにより、これまで1割で済んでいた方の負担が倍になることも。
◇ ケアマネージャーへの報酬減
要介護認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)を立てる役割を担うのがケアマネージャーですが、その報酬(支援費)が削減される方向で検討されています。
報酬が減ることで、質の高いケアマネジメントが維持できなくなる懸念があり、間接的に利用者の支援体制にも影響が及びます。
◇ 要介護1・2の「総合事業」への移行
要介護1・2の軽度者については、市町村が運営する「総合事業」へ移行する案が検討されています。
この総合事業は、自治体ごとにサービスの質や量が異なるため、地域間の格差やサービスの低下が懸念されています。
■ 高齢者が今からできる「備え」
制度の変更は個人で止められませんが、以下のような準備は可能です。
◇ 年間の介護費用を把握しておく
「どの程度の介護を、どのくらいの期間、受けることになるか」は予測が難しいですが、目安として月額2~5万円程度の自己負担がかかる場合があります。
いざというときに備えて、年間数十万円の予備費を確保しておくと安心です。
◇ 地域の介護サービスの情報を集めておく
総合事業に移行した場合、自治体によって提供内容が異なるため、事前に自分の住む地域の情報を把握しておくことが重要です。
役所の福祉課や地域包括支援センターに問い合わせて、パンフレットや相談窓口を活用しましょう。
◇ 親の介護が気になる人は、今から話し合いを
親が75歳を超えている場合、制度の改正によって「親の介護が必要になったけれど思った以上にお金がかかる」といった事態が生じかねません。
事前に親子で費用負担の考え方や、施設か在宅かなどの希望を話し合っておくと、いざという時の混乱が減ります。
■ 制度は変わる──でも備えは「今すぐ」できる
介護保険制度の改正は、「いずれ誰にでも関係してくる話」です。
自分はまだ関係ないと思っていても、親や配偶者、あるいは自分自身が予想より早く介護の当事者になる可能性があります。
2025年の変化に備えるということは、未来の生活の不安を軽くすることでもあります。
制度がどう変わるかを知り、今できる準備をひとつずつ始めていきましょう。
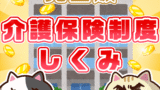



コメント