
庶民の食卓から牛肉が消える日──輸出拡大の陰で何が起きているのか
2025年7月、日本と中国の間で牛肉輸出再開に向けた協定が正式に発効されました。2001年、いわゆるBSE(牛海綿状脳症)の発生を受けて停止された日本産牛肉の対中輸出。あれから24年、ようやく中国市場に再び和牛が戻る道が開けたわけです。
ニュースでは「14億人の巨大市場」「ブランド和牛の高級輸出」といった期待に満ちた言葉が並びます。しかし、私は素直に喜べません。むしろ、「またか」「誰のための政策なんだ」と感じてしまうのです。なぜなら、今の日本の食卓を見れば明らかに、牛肉はすでに“遠い存在”になっているからです。
私自身、焼き肉屋にでも行かない限り、牛肉を買って食べる機会はほとんどありません。価格が高すぎて手が出ないし、家庭で料理するには扱いづらい。特に一人暮らしや年金生活では、わざわざ牛肉を選ぶ理由がなくなってきています。実際に、牛肉の1人あたり消費量は2000年の約7.7kgから、2022年には5.8kgへと2割以上も減少しています。
その一方で鶏肉や豚肉は安定して消費され、食卓の主役を担っています。庶民の感覚では、もはや「牛肉はたまの贅沢」。それが、今では「手の届かない高級品」になりつつあるのです。こうした現実を無視して、さらに海外への輸出を優先させることに、私は疑問を感じます。
中国市場は確かに巨大です。しかし、実際に日本産和牛を購入できる層は限られています。富裕層や中間層を含めても、せいぜい2億人程度と推定されており、これは「14億人」のごく一部。しかも中国経済は不動産バブル崩壊や若年層の失業など、深刻な構造不況に直面しています。本当に今、中国をあてにしてよいのか。これは政治家や輸出業者だけでなく、国民全体で考えるべきテーマです。
畜産農家にとって、輸出はたしかに希望でもあります。特に高品質な和牛を生産している農家にとっては、中国の富裕層マーケットは魅力的でしょう。しかし、その恩恵を受けるのはごく一部の中〜大規模農家です。小規模経営では、輸出向けの衛生管理や検疫体制に対応するだけでも負担が大きく、参加は難しいのが実情です。
また、日本の畜産業は今、飼料費の高騰、人手不足、高齢化という三重苦に直面しています。政府や農水省は「輸出を増やせば生産が増える」と言いますが、それはあまりにも楽観的です。生産量が増えない中で輸出だけを優先すれば、国内市場に回る肉は当然減ります。そして、価格はさらに高騰する──その結果、庶民の食卓から牛肉が消えてしまうのです。
すでにスーパーでは、和牛は100gあたり800円〜1000円という高値が当たり前。かつては家庭料理の定番だったすき焼きや牛丼も、いまや「外食でしか食べない」存在になりつつあります。家庭料理の中から牛肉が静かに姿を消していく。そんな光景が現実になっているのです。
私は、こうした状況を“仕方ない”とは思いません。むしろ、ここで立ち止まって「誰のための牛肉政策なのか?」を問い直すべきだと考えます。輸出の拡大も大切でしょう。しかし同時に、国内の食卓に牛肉を届ける使命も忘れてはならないはずです。高級品であっても、特別な日には手が届く──そんな存在であり続けてほしいのです。
輸出と国内供給のバランス、ブランド戦略と庶民の実感、そのどちらも見据えた誠実な農政がいま必要です。庶民の食卓に牛肉が戻ってくる日は、はたして来るのでしょうか。私は、そうであってほしいと強く願います。
中国頼みの増産は、本当に持続可能なのか?
今後もっとも懸念されるのは、政府や農水省が「中国向け輸出が拡大する」という前提のもと、畜産農家に無理な増産や設備投資を迫る可能性です。新しい牛舎、高度な衛生設備、厳格な飼養管理体制──それらは確かに輸出には必要でしょう。
しかし、そのすべては「金のなる木」が中国にあるという幻想が前提です。もし中国経済が今後さらに悪化し、輸出が止まったら? もし突然の禁輸や検疫の遅延が発生したら?
実際、中国は過去にも政治的理由で日本の食品輸入を一方的に停止した前科があります。福島の水産物、台湾産パイナップル、韓国産キムチ──“禁輸”は外交カードとして何度も使われています。
そんな不安定な市場に依存して、農家に借金を背負わせるような政策は、あまりにも無責任ではないでしょうか。輸出が止まった後に残るのは、借金と過剰設備、そして行き場を失った牛たちです。これでは「共倒れ」以外の未来が見えません。
誰がこの流れを止めるのか
問題なのは、こうしたリスクに対する政治の鈍感さです。現実を直視せず、「中国はチャンスだ」と浮かれる親中派の政治家、そしてそれに唯々諾々と従う農水省の官僚たち。この構図が続く限り、また同じ失敗が繰り返されるでしょう。
本当に農家を守るなら、まず国内の需要と食文化を大切にするべきです。庶民の食卓に牛肉を戻し、安定した内需を土台にしたうえで、余力としての輸出に取り組む──その順序を間違えてはいけません。
政治とは、夢を語る前に現実を守るもの。私はそう思います。
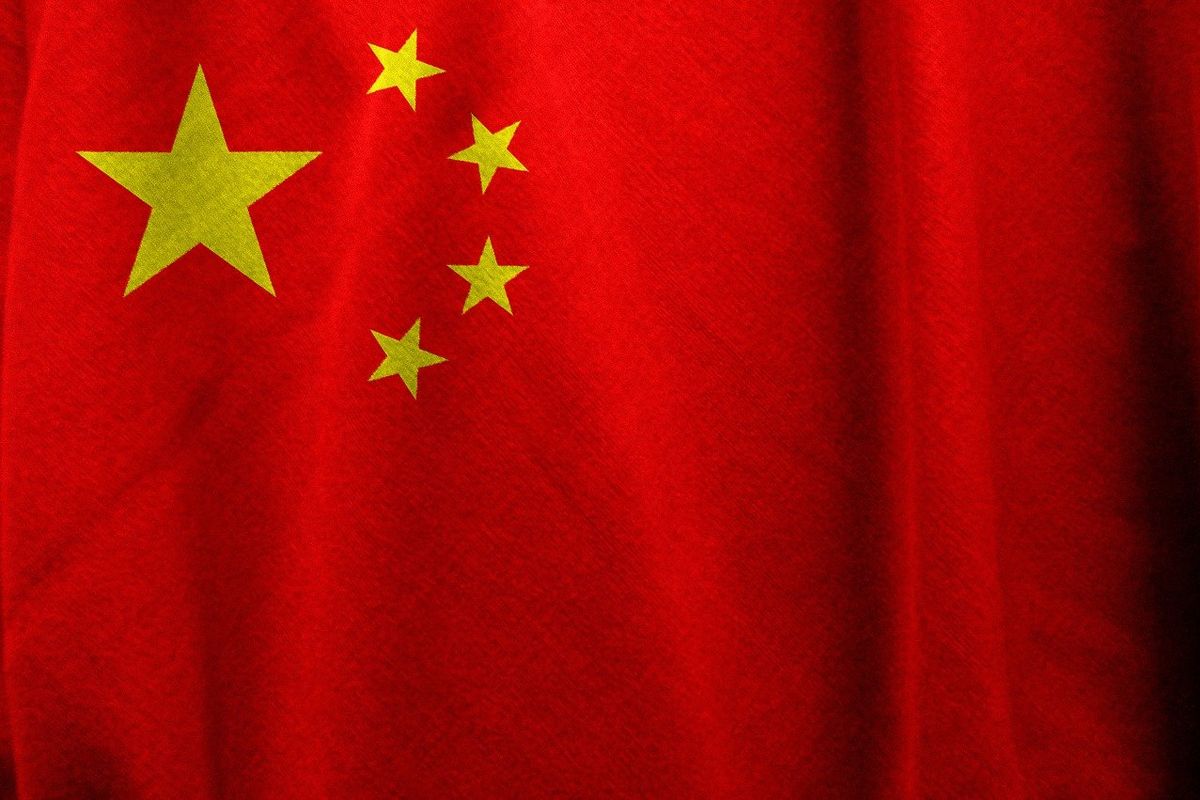


コメント