9月半ばに帰省し東京へは戻りません。東京での食生活は自分でも酷いと感じているので、田舎で暮らすようになればかなり見直したいと考えています。パンや緬などの小麦食は極力避け、米食中心の元来の日本人食、それもかなりな粗食になると思います。
もともと料理には興味があり、上京する前は3食自炊していました。そんなこともあって、最近は食に関する動画などを見て学んでいます。この動画は江戸時代から明治にかけての食について素晴らしくまとめられているので参考にさせていただきました。
以下は動画の内容をまとめたものです。
江戸時代から明治時代にかけて、日本の文化や産業、生活様式は大きく変革しました。食生活もその一環であり、海外から新しい食文化が流入し、日本独自のアレンジが加わることで劇的な変化が生まれました。本記事では、江戸から明治への食事事情の変化、そして都市部と地方の食生活の格差について詳しく解説します。
江戸時代の肉食文化と制限の背景
江戸時代は仏教の影響が強く、肉食が避けられていたと思われがちですが、実際には鹿や狸、猪、豚などが食べられていました。江戸や長崎では豚の飼育も記録されており、薬や食材として肉が利用されていました。
ただし、武士や庶民では宗教や社会的慣習により肉食が制限され、日常的に肉を食べる機会は限られていました。保存食として干肉やカス漬けも存在し、牛は労働力として重視されたため食用にはされにくかったのです。
江戸時代の食生活と「江戸わずらい」
江戸時代の食事は白米中心で、成人男性は1日5合ほどを食べていました。おかずは野菜や味噌汁、漬物が主で、栄養バランスが偏り、ビタミンB1不足から脚気(かっけ)が流行。この病は「江戸わずらい」と呼ばれました。
玄米を食べれば予防できたものの、白米が好まれたため栄養不良に陥りました。ビタミンB1を補う蕎麦は江戸で人気を博し、栄養不足の緩和に役立ちました。
明治時代の食生活と脚気撲滅運動
明治時代になっても白米中心の食事は続き、明治3年(1870年)頃には脚気が再び大流行。明治10年の西南戦争では兵士に多くの脚気患者が出て社会問題となりました。
海軍軍医・高木兼寛による改善と海軍カレーの誕生
海軍軍医・高木兼寛は船ごとの脚気発生率の差に着目し、食事の栄養バランス改善を提案。洋食を取り入れる実験で脚気は大幅に減少しました。この成果は海軍全体に広まり、パン食からご飯にカレールーをかける日本式「海軍カレー」が誕生しました。
陸軍の缶詰活用と鮭缶の効果
陸軍では保存性と栄養価の高い缶詰を導入。北海道・石狩缶詰所で生産された鮭缶はビタミンB1が豊富で、兵士の脚気予防に大きく貢献しました。
都市部と地方の食生活格差
都市部では食生活が改善され脚気も減少しましたが、農村部では白米中心の栄養不足が続きました。群馬県の富岡製糸場では工女に白米が提供され、これが脚気の原因となりました。
農村部では雑穀畑が桑畑に転換され、栄養バランスがさらに悪化。結果として、脚気は地方で長く続き、明治時代全体の社会問題となりました。
明治時代後半の洋食文化と調味料の普及
明治後半になると、西洋料理が一般家庭に浸透しました。高等女学校での家庭科授業を通じて和洋折衷料理が広まり、西洋料理のレシピ本も庶民に支持されました。
洋食の普及とともに、食用油やウスターソース、ケチャップといった新しい調味料が登場。特にケチャップは1896年に横浜の清水屋が国産化し、その後カゴメが本格的に製造販売しました。
牛鍋・すき焼きの登場と人気
牛鍋(すき焼き)は文明開化の象徴的料理として広まり、関東では牛鍋、関西ではすき焼きと呼ばれ、それぞれ独自のスタイルが発展しました。
明治時代の食文化が残したもの
明治時代を通じ、日本は西洋文化を取り入れつつ独自の食文化を形成しました。都市ではポークカレーやカツカレーが流行し、地方では雑穀中心の食生活が続くなど、都市と地方の食の格差は広がりました。これらの変化は社会全体の変革を映し出し、現代の日本食文化の基礎となりました。

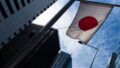

コメント