高齢化が加速する日本社会において、認知症を抱える高齢者の数は年々増加しています。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を患うとされており、地域や家庭を含めた包括的なケア体制の強化が求められています。
こうした中、2025年7月に開催された「第30回日本老年看護学会」で発表されたのが、生成AIを活用した認知症ケア支援システム『MorsonSmartQ&A(モーソンスマートQ&A)』です。人間の判断を補助する形でAIが情報提供を行うこの仕組みは、医療・介護業界の人手不足や知識格差を補う可能性を秘めています。
認知症ケアの現場が抱える課題
認知症の症状は、記憶障害、判断力の低下、感情の不安定さなど多岐にわたり、本人も周囲も戸惑うことが少なくありません。特に介護現場では以下のような声が多く聞かれます:
- 「この言動は病気の進行?それとも一時的な混乱?」
- 「家族にどう説明すれば納得してもらえるのか…」
- 「新人スタッフにうまく教えられない」
ベテランの感覚や経験に頼る部分が大きく、スタッフ間で対応にばらつきが出ることもしばしばです。さらに、情報共有の時間や教育コストも現場の大きな負担となっています。
「MorsonSmartQ&A」の仕組みと特徴
「MorsonSmartQ&A」は、医療・福祉の専門用語や最新研究、臨床現場での実例を学習した生成AIによって、スタッフが抱える疑問に即座に回答するQ&Aシステムです。入力された質問に対して、AIが信頼性の高い情報や推奨される対応例を提示します。
たとえば「利用者が深夜に頻繁にトイレに行きたがる」という相談に対して、脱水症状の可能性、薬の副作用、認知症特有の不安行動などを分析した上でのアドバイスが得られる設計になっています。
現場での導入事例──“もう一人の相談役”として
実際に導入が進む施設では、以下のような活用シーンが報告されています。
- 新人介護士が「この対応で大丈夫か」と不安な時、AIが正確なガイドラインと対応例を示し、判断を後押し
- 夜間の少人数体制時に、緊急時対応の可否をその場で確認できる
- 多職種間カンファレンスでの意見整理に使われ、共通認識の形成に貢献
ベテラン看護師の一人は「まるで隣にもう一人の専門家がいてくれる感覚。忙しいときほど心強い」とコメントしています。
在宅介護への応用にも期待
今後の展開として期待されるのが、一般家庭への導入です。高齢の親を介護する家族が、AIを使って即時に専門的なアドバイスを得られれば、精神的な負担の軽減にもつながります。
「夜中に母が同じことを何度も聞いてくる…これは病気の進行?」「この行動、医師に相談するレベル?」──こうした悩みを抱える家族にとって、AIは“家庭内の看護師”のような役割を果たしてくれるかもしれません。
AIにできること、できないこと
もちろん、AIは万能ではありません。人間の感情に寄り添う力や、表情や雰囲気から察する能力は、まだまだ人間に及びません。しかし、情報の正確さ・スピード・公平性においては、大きな力を発揮します。
適切に使えば、AIは現場を支える「もうひとつの柱」となり得る存在なのです。
まとめ:AIと人が協働する未来へ
超高齢社会の日本では、認知症ケアの質と量の両立が今後の鍵となります。「MorsonSmartQ&A」は、その課題をテクノロジーの力で乗り越える新たなアプローチです。
人の温かさと、AIの冷静な知見。この二つがうまく融合すれば、より持続可能で安心できるケアの形が見えてくるでしょう。
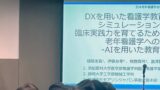



コメント