「60代・70代からでも資格が取れるのか?」そう考える方が年々増えています。年齢を重ねてからの勉強は不安もありますが、実際に合格し、人生の新しい一歩を踏み出すシニアも少なくありません。今回は人気の2大資格──宅建士と行政書士について、現実的な視点で比較してみましょう。
宅建士──試験は取りやすいが、仕事にするには難しさも
宅建士(宅地建物取引士)は毎年20万人以上が受験する人気資格で、合格率は15%前後。学習範囲が比較的狭く、60代からの挑戦者も少なくありません。
宅建士として登録するには、2年以上の実務経験、または登録実務講習の修了が必要です。登録実務講習は通信学習+2日間のスクーリングという形式が基本ですが、実際はスクーリング2日間で完結する形が主流で、予習程度の通信学習のみで済むケースがほとんどです。
ただし、宅建士の資格を持っているだけでは仕事につながりにくく、宅建業を営むには別途開業手続きや資金、事務所などの要件が必要です。独立開業のハードルは高めです。
一方で、不動産会社が宅建士を非常勤やスポットで募集している例もあり、高齢者にもニーズがある可能性はあります。名義貸しではなく、重要事項説明などの限定業務を任せるケースがあるようです。最近ではリモート対応による「IT重説(重要事項説明)」のニーズも高まっており、自宅にいながら資格を活かすチャンスも生まれています。
行政書士──難易度は高いが、独立開業しやすい
行政書士は法律系国家資格で、合格率は10%前後。試験範囲は広めですが、文章読解や記述力が問われるため、年齢的な不利は少ないといえます。
最大の魅力は、合格後すぐに独立開業できる点です。自宅開業も可能で、登録すれば「街の法律家」として書類作成や相談業務ができます。行政書士の業務は多岐にわたり、相続や遺言、建設業許可、農地転用、空き家の利活用支援など、地域に密着した仕事も可能です。
ただし、仕事が得られるかどうかは本人の営業力や人脈、地域との関係に大きく左右されます。パソコン操作やウェブでの情報発信が苦手な人にはやや難しい面もありますが、逆に得意な方にとっては年齢に関係なく活躍できる分野でもあります。
どちらを選ぶべきか?
宅建士は「取りやすいが仕事につながりにくい」、行政書士は「取りにくいが仕事にはつながりやすい」と言われます。どちらも一長一短があり、自分の性格や目的に合わせて選ぶのが現実的です。
仕事として活かすだけでなく、「頭の体操」「自分の生活への応用」「人生経験の証明」として資格を目指す人も増えています。知識を得ることで家族の相談に乗れたり、相続や不動産に関する判断が的確にできるようになったりするのも大きなメリットです。
資格取得がもたらすこれからの展望
高齢になってからの資格取得は、不安もある反面、大きな達成感や新しい展望を与えてくれます。勉強を通して日々の生活にリズムが生まれ、「今日はこれだけ進めた」という充実感や、少しずつ知識が増えていく喜びを実感することができます。
特に、頭を使う学習は“脳の体操”としても有効で、忘れていた集中力や知的好奇心を呼び起こしてくれます。合格そのものももちろん目標ですが、それ以上に「学ぶ過程」に意味があると感じる人も多く、勉強している期間自体が心の張りや生きがいになることもあるでしょう。
年齢を理由にあきらめるのではなく、今だからこそできる挑戦として、宅建士や行政書士を検討してみてはいかがでしょうか。新たな学びが、人生後半の充実につながる可能性は十分にあります。
人生後半、学びの先にある“もうひとつの楽しみ”
資格の勉強を通じて得た自信や行動力は、別の分野への挑戦にもつながります。知識や経験を土台にしながら、自分らしい暮らしや小さなビジネスに踏み出す人も少なくありません。以下のような取り組みも、高齢期にこそおすすめできる生き方です。
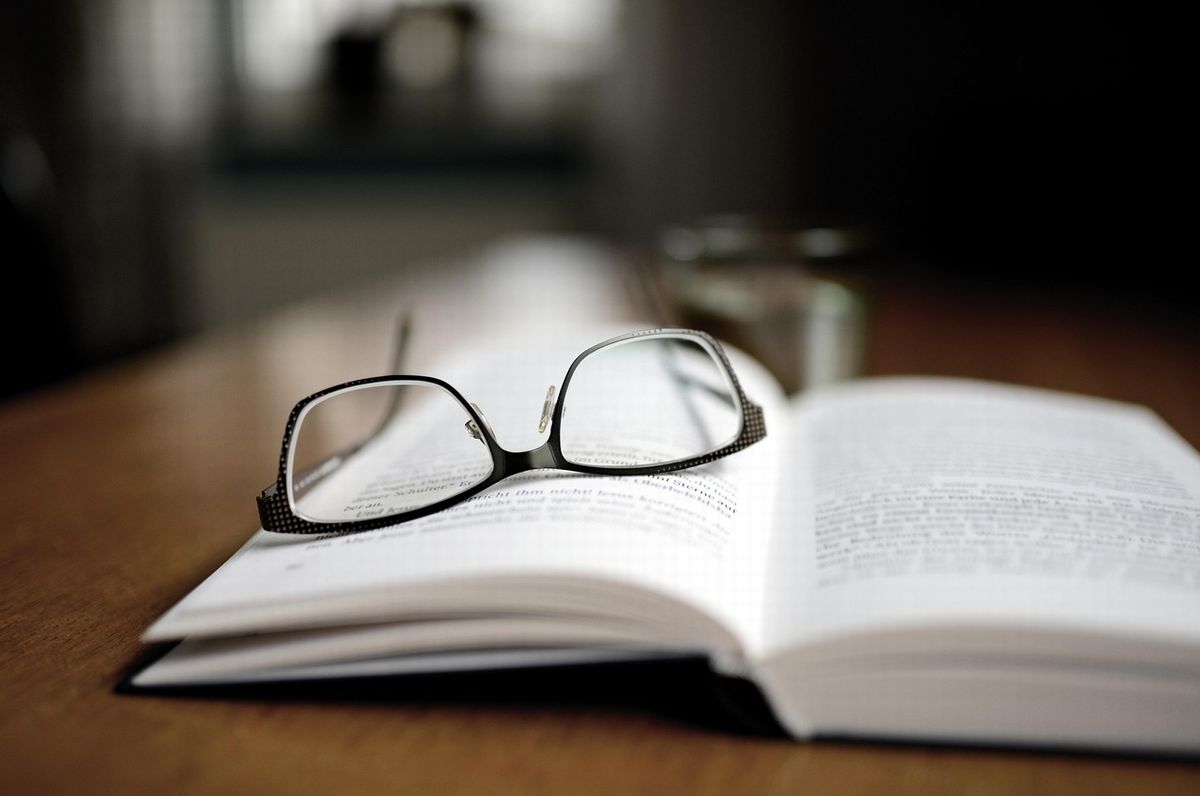


コメント